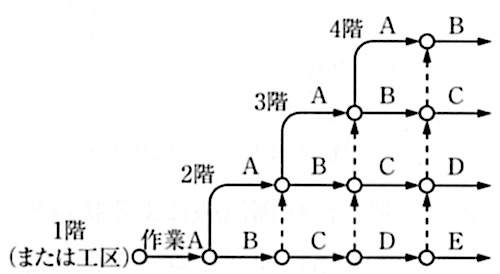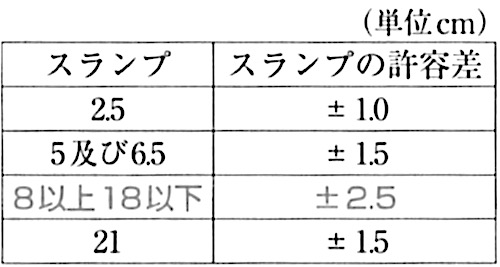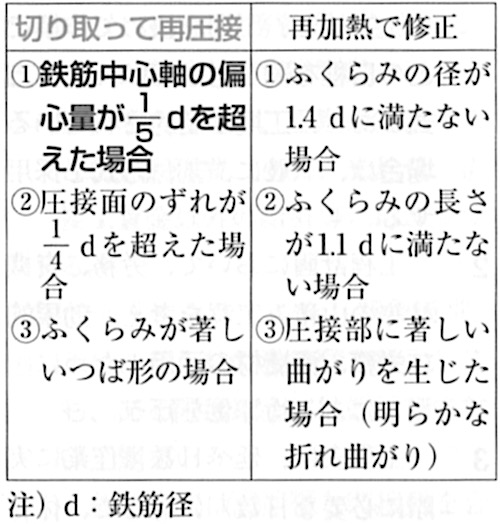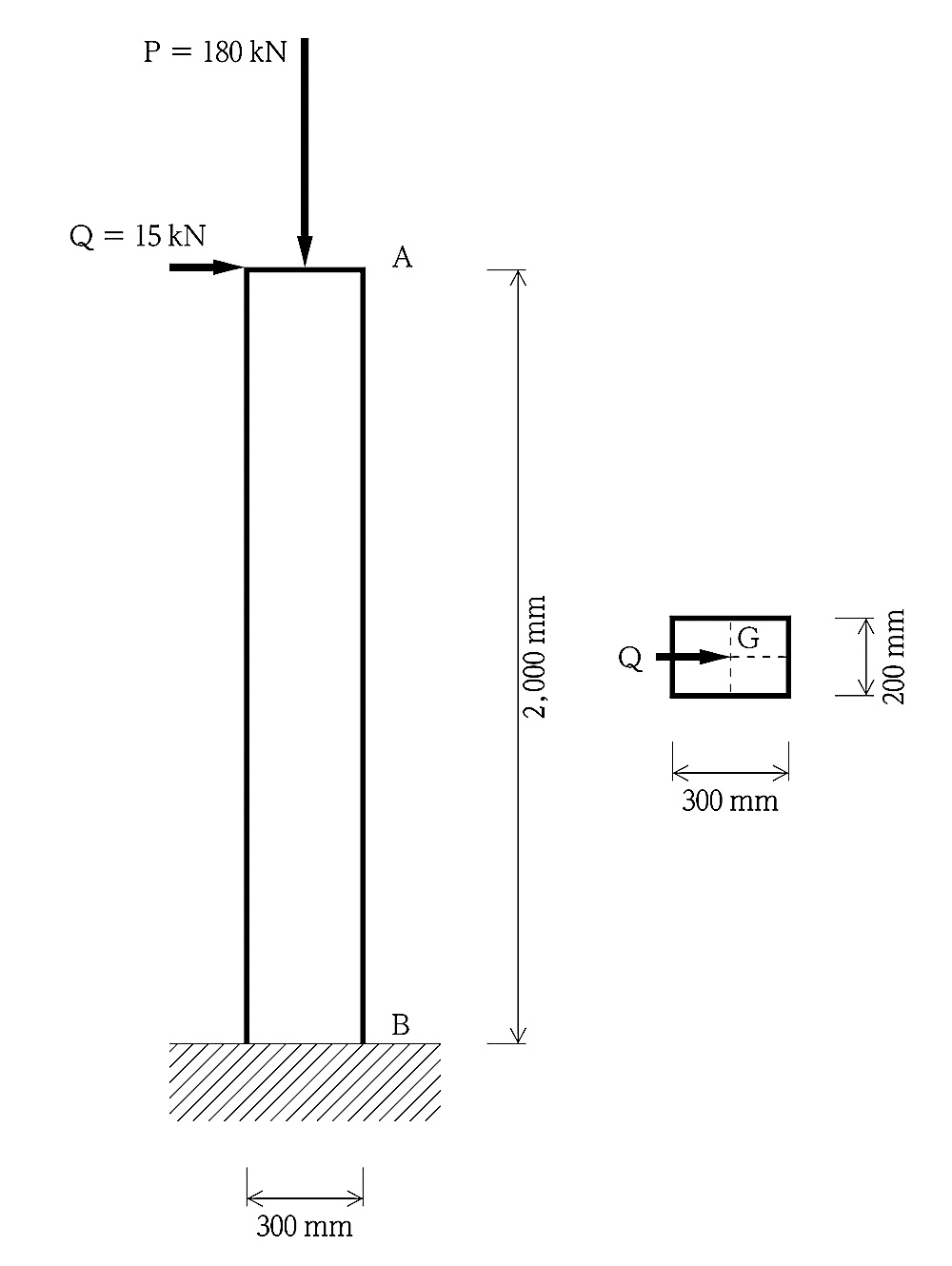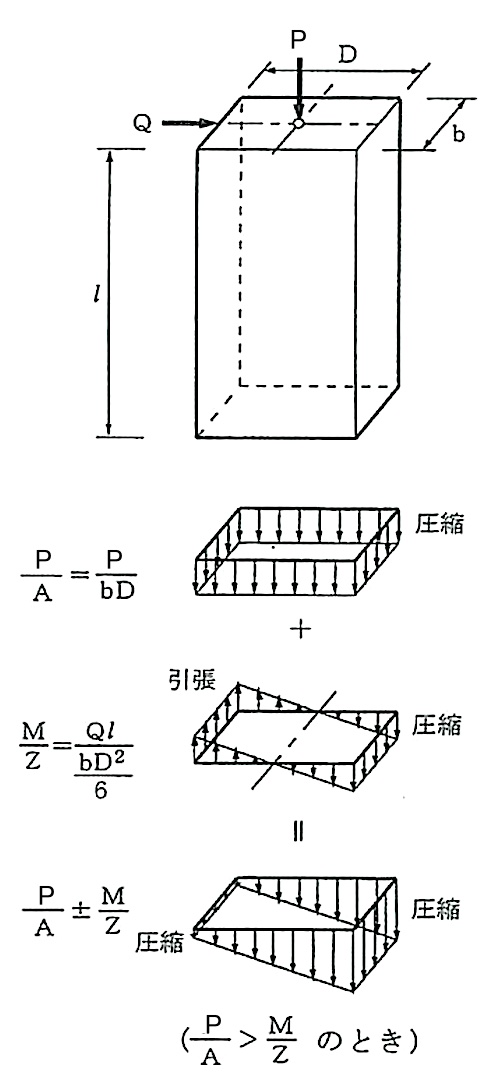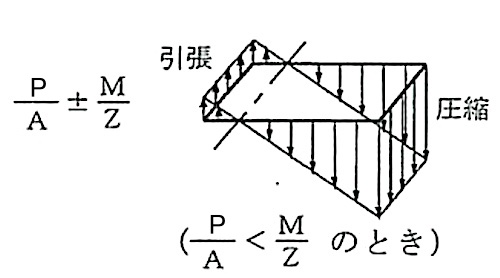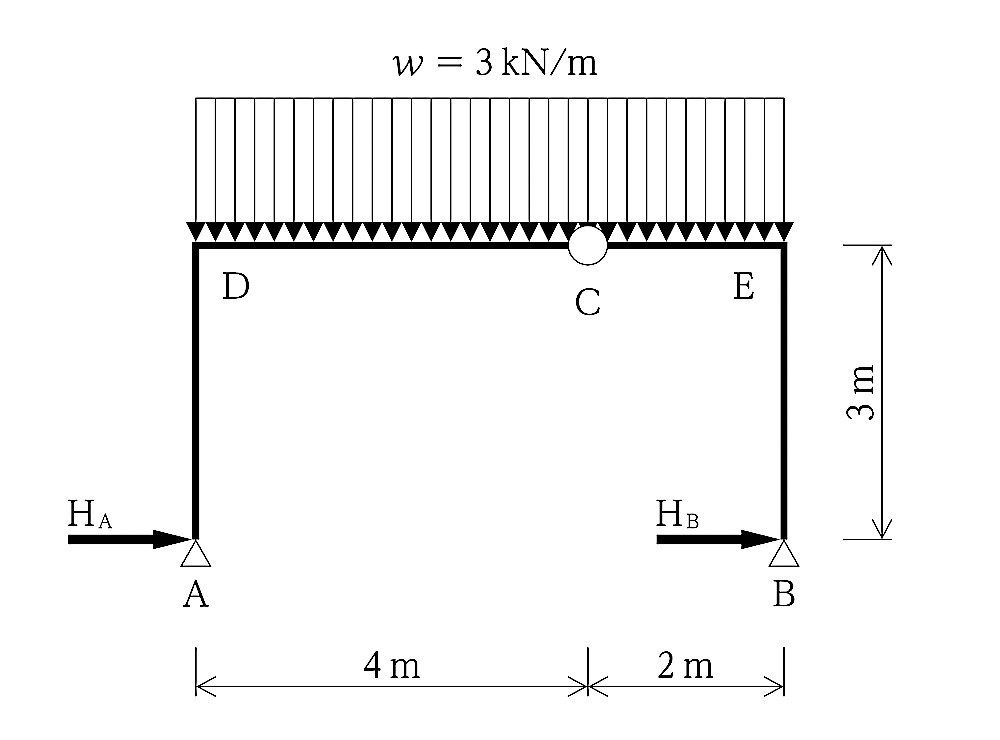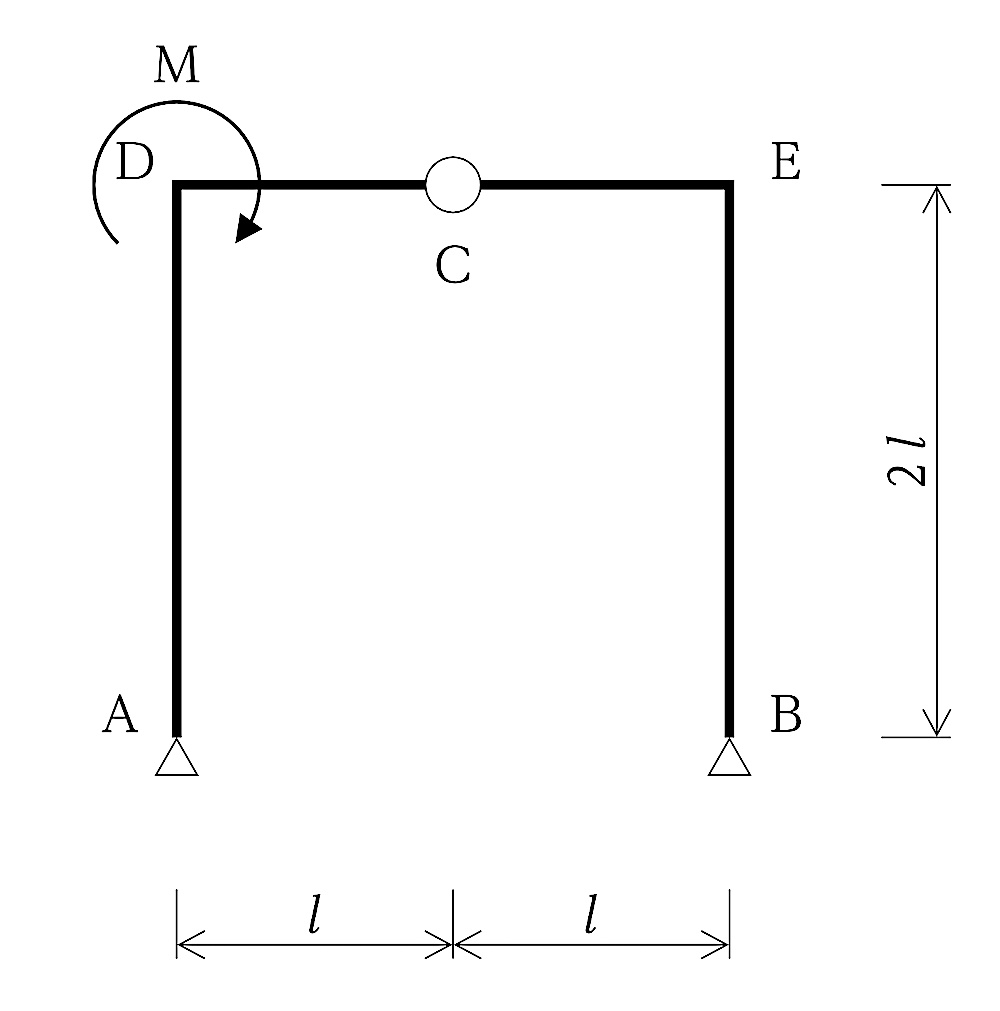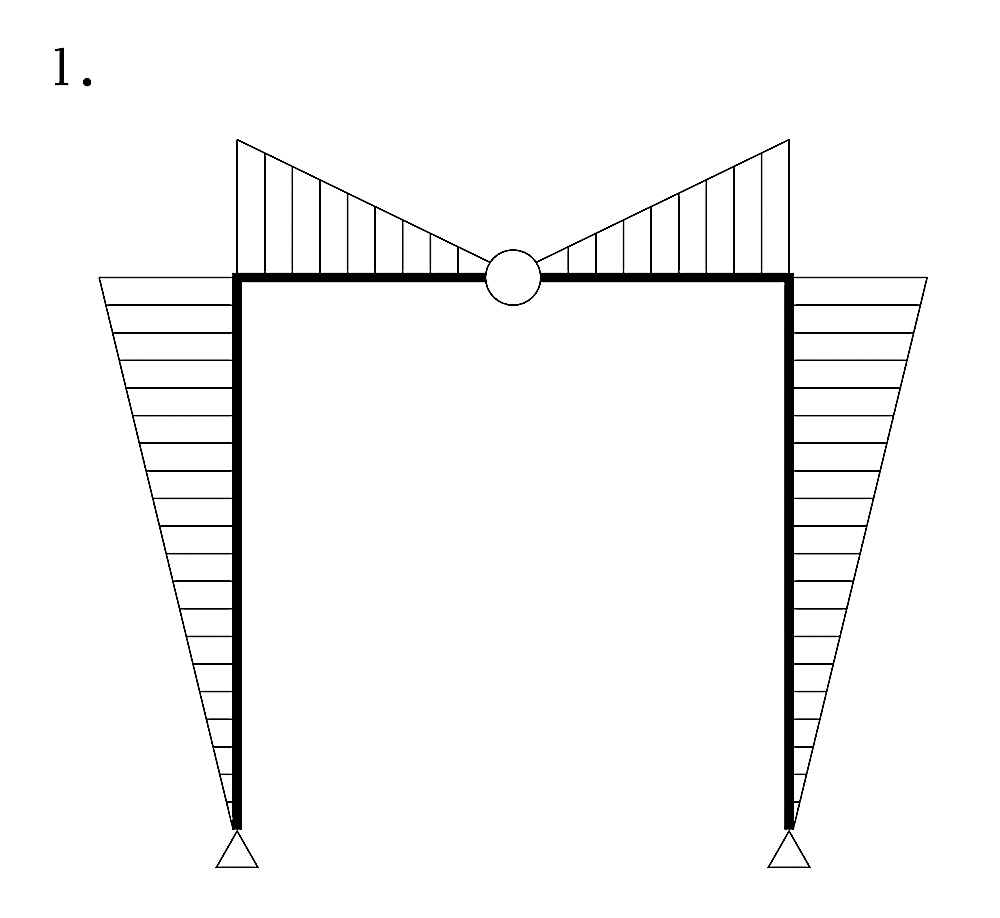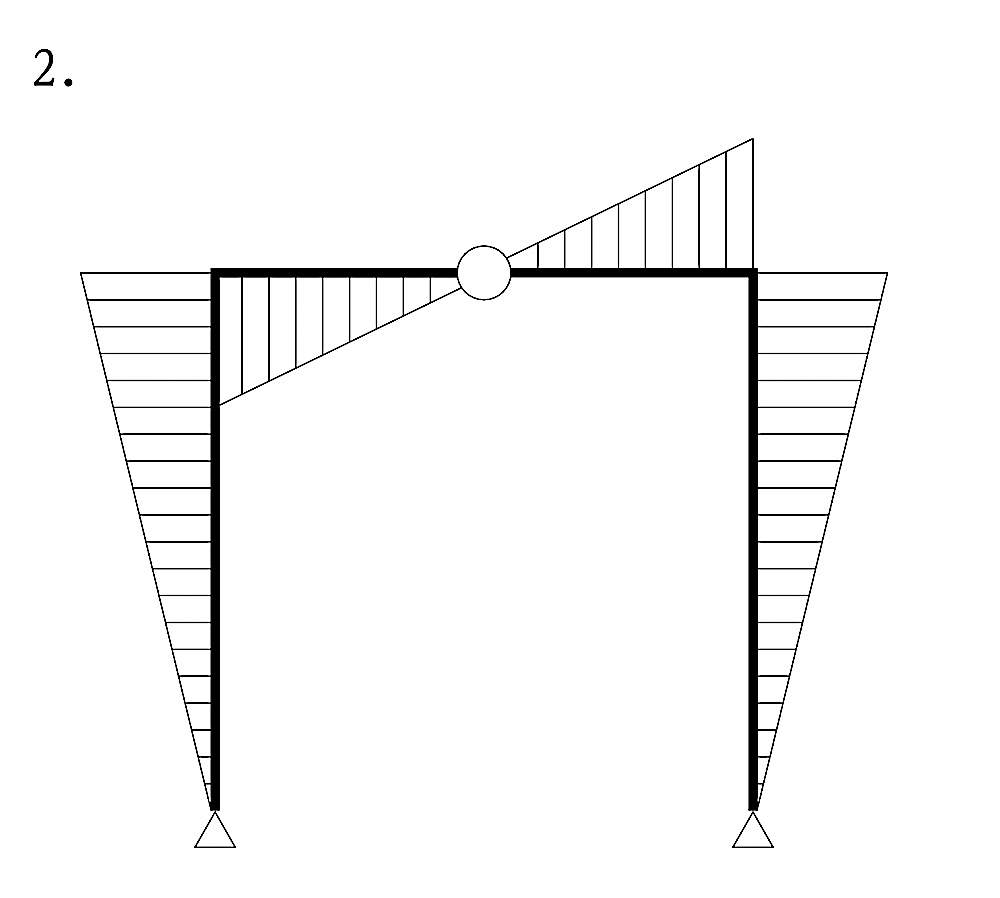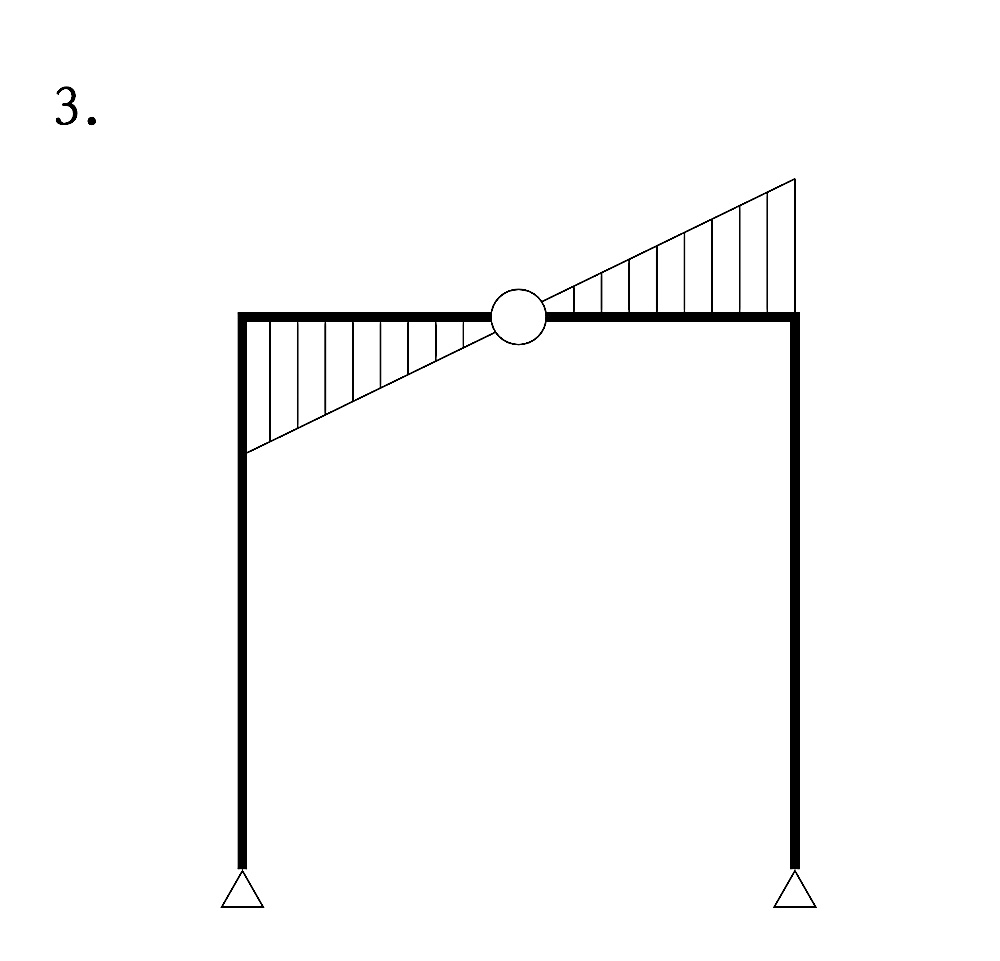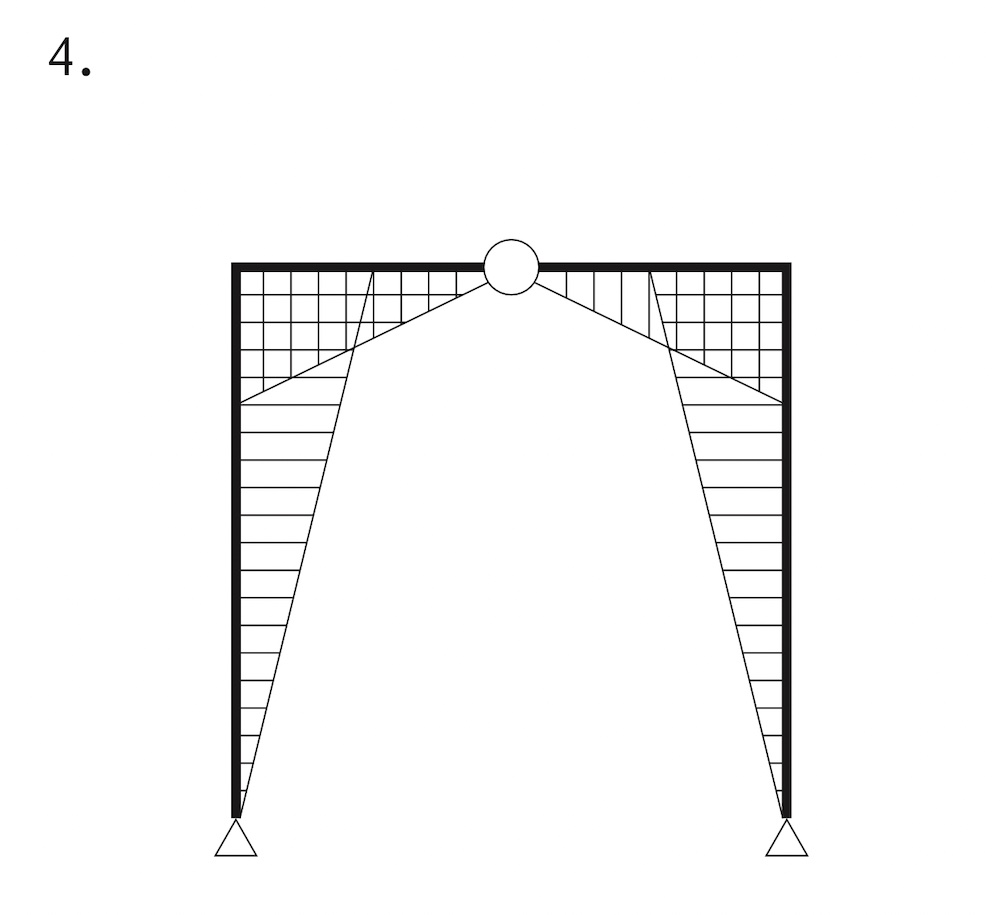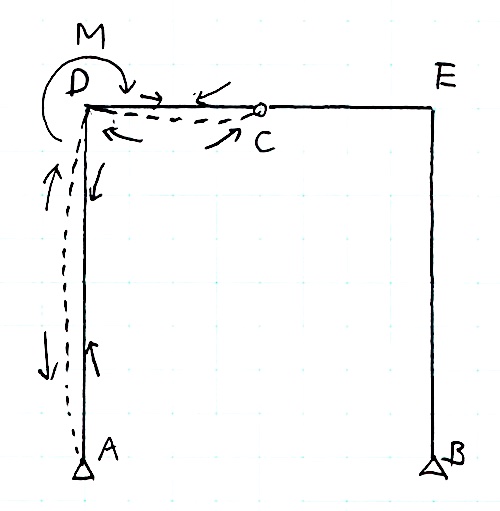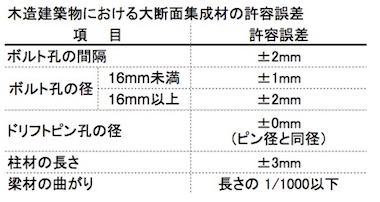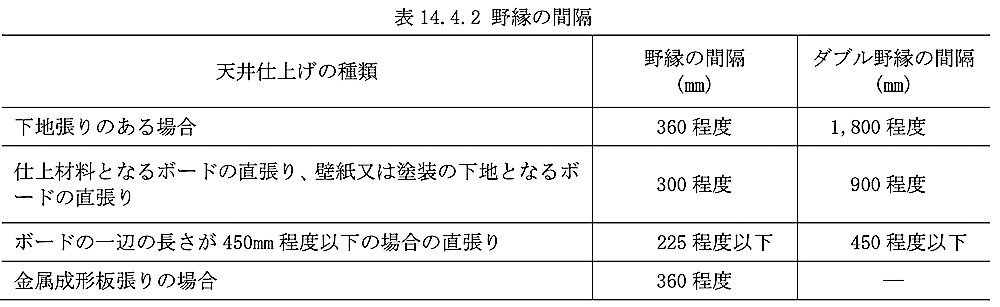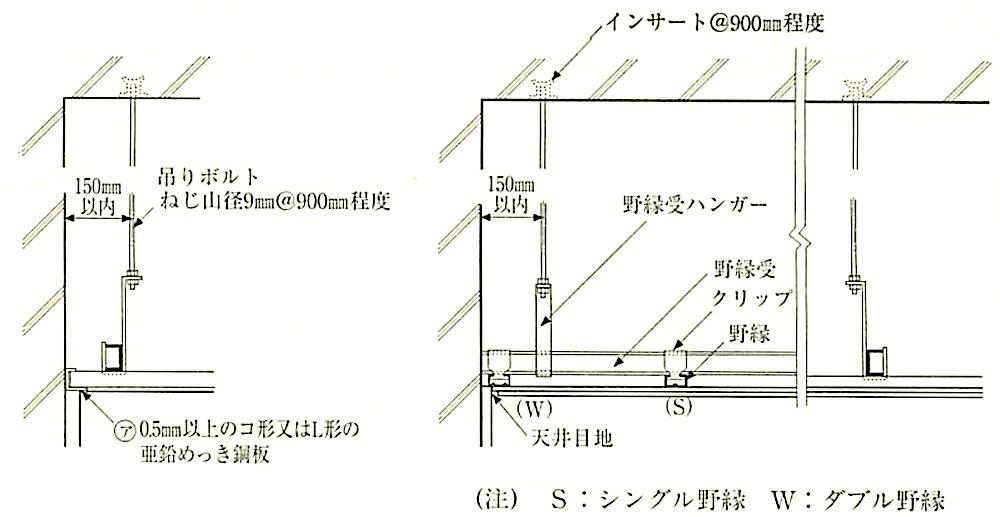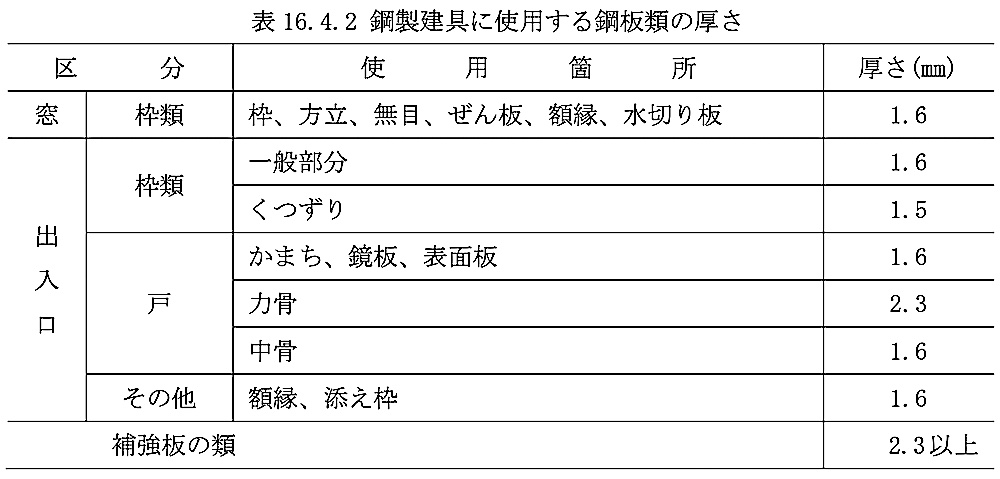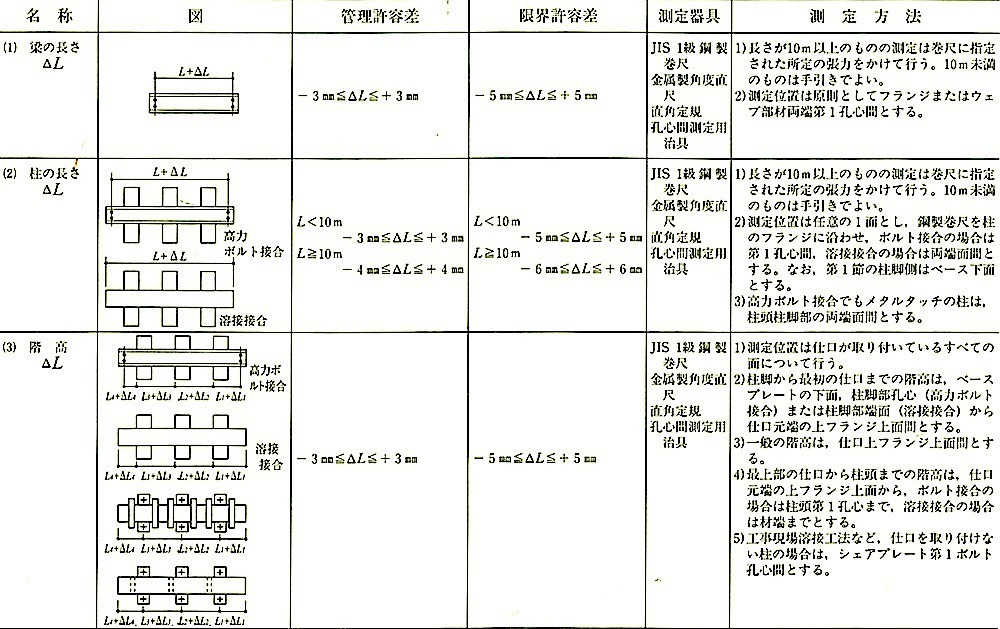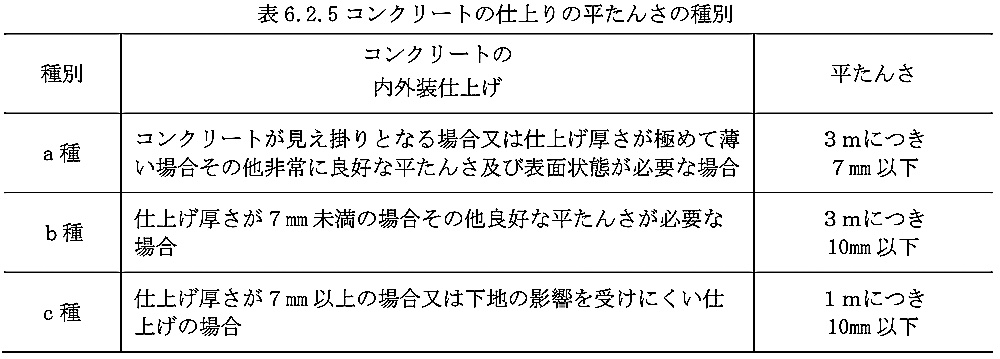令和4年 1級建築施工管理技士 一次 解答 解説 問題8
※ 問題番号[ No.61 ]~[ No.72 ]までの 12 問題のうちから、8問題を選択し、解答してください。
[ No.61 ]
次の記述のうち、「建築基準法」 上、誤っているものはどれか。
1.鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅においては、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する特定工程に係る工事を終えたときは、中間検査の申請をしなければならない。
2.木造3階建ての戸建て住宅を、大規模の修繕をしようとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
3.確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から5日以内に、建築主事に到達するように検査の申請をしなければならない。
4.床面積の合計が 10 m2 を超える建築物を除却しようとする場合においては、原則として、当該除却工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条の3第1項)
同条第一号に、「階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配筋する工事の工程のうち政令で定める工程」と規定されている。
2.◯
木造3階建ての戸建て住宅を、大規模の修繕をしようとする場合において、建築主は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定その他建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものに適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)
3.×
建築基準法第7条第1項、第2項に次のように規定されている。
「建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。」
「前項の規定による申請は、第6条第1項の規定による工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかったことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」
4.◯
建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が 10 m2 以内である場合においては、この限りでない。(建築基準法第15条第1項)
[ No.62 ]
次の記述のうち、「建築基準法」 上、誤っているものはどれか。
1.建築監視員は、建築物の工事施工者に対して、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。
2.建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。
3.建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。
4.特定行政庁が指定する建築物の所有者又は管理者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
特定行政庁、建築主事または建築監視員 は、建築物の工事の計画もしくは施工の状況等に関する 報告 を、工事施工者に求めることができる。(建築基準法第12条第5項)
2.×
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人などに対し、当該工事の施工の停止を命じ、又は、違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。(建築基準法第9条第1項)
3.◯
建築物の所有者、管理者または占有者 は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を 常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。(建築基準法第8条第1項)
4.◯
特定行政庁が指定するものの所有者は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省の定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士または建築物調査員資格者証の交付を受けている者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。(建築基準法第12条第1項)
<!― 12条点検 第1項 特定建築物定期調査・外壁打診検査 第3項 建築設備定期検査、防災設備定期検査、昇降機等定期検査 –>
[ No.63 ]
避難施設等に関する記述として、「建築基準法施行令」 上、誤っているものはどれか。
1.小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。
2.映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。
3.回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から 30 cm の位置において測らなければならない。
4.両側に居室がある場合の、小 学校の児童用の廊下の幅は、2.3 m以上 としなければならない。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500m2を超える建築物の居室等及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段等の部分には、非常用の照明装置を設けなければならないが、学校、病院の病室等は除かれている。(建築基準法施行令第126条の4第三号)
2.◯
劇業、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。(建築基準法施行令第125条第2項)
3.◯
回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から 30 cmの位置において測るものとする。(建築基準法施行令第23条第2項)
4.◯
両側に居室がある場合の、小学校の児童用の廊下の幅は、2.3 m以上としなければならない。(建築基準法施行令第119条)
[ No.64 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」 上、誤っているものはどれか。
1.特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち、指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業及び造園工事業の5業種である。
2.一般建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して 10年以上の実務の経験を有する者を、その営 業 所ごとに置く専任の技術者とすることができる。
3.工事一件の請負代金の額が 500 万円に満たない建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
4. 特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が 6,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち、指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、菅工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業の7業種である。(建設業法施行令第5条の2)
2.◯
建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上の実務の経験を有する者を、一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。(建設業第7条第二号)
3.◯
政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が 500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、1,500万円)に満たない工事は、建設業の許可を受けなくてもよい。(建設業第3条第1項ただし書、同施行令第1条の2)
4.◯
特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が政令で定める金額(建築工事業の場合 6,000万円)以上となる下請契約を締結してはならない。(建設業第16条第1項)
[ No.65 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」 上、誤っているものはどれか。
1.注文者は、工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事の請負契約の方法が随意契約による場合であっても、契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15 日以上を設けなければならない。
2.元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から 30日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
3.特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
4.元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
請負契約の方法が随意契約による場合であっても、注文者は、工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事の契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15 日以上を設ける必要がある。(建設業法第20条第4項、同施行令第6条第1項第三号)
2.×
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。(建設業法第24条の4第1項)
3.◯
特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金または貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。(建設業法第24条の6第3項)
4.◯
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。(建設業法第24条の2)
[ No.66 ]
監理技術者等に関する記述として、「建設業法」 上、誤っているものはどれか。
1.専任の監理技術者を置かなければならない建設工事について、その監理技術者の行うべき職務を補佐する者として政令で定める者を工事現場に専任で置く場合には、監理技術者は2つの現場を兼任することができる。
2.専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して7年を経過しない者でなければならない。
3.建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、現場代理人の設置にかかわらず、主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
4.主任技術者及び監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上 の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
専任の監理技術者を置かなければならない建設工事について、その監理技術者の行うべき職務を補佐する者として政令で定める者を工事現場に専任で置く場合には、監理技術者は2つの現場を兼任することができる。(建設業法第26条第3項ただし書)
2.×
専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。(建設業法第26条第5項、同施行規則第17条の9)
<!― 監理技術者の資格の有効期間は5年であるため、7年以内ではない。(建設業法第3条第3項)―>
3.◯
建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、現場代理人の設置にかかわらず、主任技術者または監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条)
4.◯
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。(建設業法第26条の4)
[ No.67 ]
労働契約に関する記述として、「労働基準法」 上、誤っているものはどれか。
1.使用者は、労働者の退職の場合において、請求があった日から、原則として、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2.労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な契約期間を定めるもののほかは、原則として、3年を超える契約期間について締結してはならない。
3.使用者は、労働者が業務上負傷し、療養のために休業する期間とその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても解雇してはならない。
4.就業のために住居を変更した労働者が、省 令により明示された労働条件が事実と相違する場合で労働契約を解除し、当該契約解除の日から 14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。(労働基準法第23条第1項)
2.◯
労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な契約期間を定めるもののほかは、3年を超える期間について締結してはならない。(労働基準法第14条)
3.×
解雇制限について、使用者は、労働者が教務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合または天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでないと規定されている。(労働基準法第19条第1項)
<!― 労働基準法の解雇制限により、労働者が業務上負傷した場合は、休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。なお、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は解雇できる。(労働基準法第19条第1項) ―>
4.◯
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から 14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。(労働基準法第15条第3項)
[ No.68 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
1.元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者でなければならない。
2.安全衛生責任者は、安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならない。
3.特定元方事業者は、統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。
4.統括安全衛生責任者は、その事業の実施を統括管理する者でなければならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。(労働安全衛生規則第18条の3)
2.×
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条)
安全衛生責任者の資格要件は、定められていない。
3.◯
事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもののうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行う者(「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。(労働安全衛生法第15条第1項)
4.◯
統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。(労働安全衛生法第15条第2項)
[ No.69 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」 上、誤っているものはどれか。
1.事業者は、労働者を雇い入れたときは、原則として、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2.事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
3.事業者は、特別教育を必要とする業務に従事させる労働者が、当該教育の科目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有すると認められるときは、当該科目についての特別教育を省略することができる。
4.事業者は、建設業の事業場において新たに職務に就くこととなった作業主任者に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項について、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行なわなければならない。(労働安全衛生法第59条第1項)
2.◯
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行うように努めなければならない。(労働安全衛生法第60条の2第1項)
3.◯
雇入れ時などの教育について、事業者は、前項各号に掲げる事項の全部または一部に関し十分な知識及び技能を有すると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができると規定されている。(労働安全衛生規則第35条第2項)
4.×
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条)作業主任者ではない。
[ No.70 ]
次の記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 上、誤っているものはどれか。
1.建設資材廃棄物の再資源化等には、焼却、脱水、圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為が含まれる。
2.建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。
3.対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
4.分別解体等には、建築物等の新築工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為が含まれる。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
この法律において建設資材廃棄物について「縮減」とは、焼却、脱水、圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をいい、「再資源化等」とは、再資源化及び縮減をいう。(建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律第2条第7項、第8項)
2.◯
建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。(建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律第5条第2項)
3.×
対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。都道府県知事への報告は定められていない。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、建設リサイクル法)第18条)
4.◯
この法律において「分別解体等」とは、次の各号に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める行為をいう。建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事(以下「新築工事等」という。)において、当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為である。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第3項第二号)
[ No.71 ]
「騒音規制法」 上、指定地域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として、誤っているものはどれか。ただし、作業は、その作業を開始した日に終わらないものとする。
1.特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業の実施の期間や騒音の防止の方法等の事項を、市町村長に届出をしなければならない。
2.くい打機をアースオーガーと併用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。
3.さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が 15kW 以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。
4.環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 70 kW以上 のトラクターショベルを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設業の開始の日の7日前までに、環境省令が定めるところにより、
①氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②建設工事の目的に係る施設または工作物の種類
③特定建設作業の場所及び実施の期間
④騒音の防止の方法
⑤その他環境省令で定める事項について
市町村長に届け出なければならない。(騒音規制法第14条第1項)
2.×
くい打機で使用する作業のうち、くい打機をアースオーガーと併用する作業は、特定建設作業から除かれている。(騒音規制法施工令別表第2第一号)
3.◯
さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が 15kW 以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出は必要である。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第四号)
4.◯
環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 70 kW以上のトラクターショベルを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第七号)
[ No.72 ]
貨物自動車を使用して分割できない資材を運搬する際に、「道路交通法」 上、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可を必要とするものはどれか。ただし、貨物自動車は、軽自動車を除くものとする。
1.長さ 11 m の自動車に、車体の前後に 0.5 m ずつはみ出す長さ 12 m の資材を積載して運搬する場合
2.荷台の高さが1m の自動車に、高さ 3mの資材を積載して運転する場合
3.積載する自動車の最大積載重量で資材を運搬する場合
4.資材を看守するため必要な最小限度の人員を、自動車の荷台に乗せて運搬する場合
答え
2
[ 解答解説 ]
1.不要
積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあっては、その乗車装置又は積載装置の長さに0.3mを加えたもの)を超えないことと規定されている。(道路交通法施行令第22条第三号イ)また、積載物の前後のはみ出しは、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えないことと規定されている。(道路交通法施行令第22条第四号イ)長さ11mの自動車に、車体の前後に 0.5mずつはみ出す長さ12mの資材を積載して運搬する場合は、積載物の長さ12mは 11 × 11 =12.1m以下、積載物の前後のはみ出し0.5mは 11 × 0.1 =1.1m以下であるので、許可は不要である。
2.必要
積載物の高さは、3.8mからその自動車の積載をする場所を減じたものを超えないことと規定されており、荷台の高さが1mの自動車に、高さ 3.0mの資材を積載して運転する場合は、高さ3.8m以上なので、許可は必要である。(道路交通法施行令第22条第三号ハ)
3.不要
車両の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員または積載物の重量、大きさもしくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、または積載をして車両を運転してはならない。制限を超えてなければ許可は不要である。(道路交通法第57条第1項本文)
4.不要
積載された資材を看守するため、必要な最小限度の人員として1名を荷台に乗車させて運転する場合は、道路交通法の規定により不要である。(道路交通法第55条第1項ただし書)