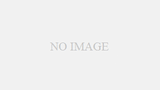[ No.45 ]
品質管理に用いる図表に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1. 特性要因図は、特定の結果と原因系の関係を系統的に表し、重要と思われる原因への対策の手を打っていくために用いられる。
2. 系統図は、目的を設定し、それを達成するための手段を系統的に展開した図である。
3. ヒストグラムは、対応する2つの特性を横軸と縦軸にとり、観測値を打点して作るグラフ表示で、主に2つの変数間の相関関係を調べるために用いられる。
4. パレート図は、項目別に層別して、出現度数の大きさの順に並べるとともに、累積和を示した図である。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
2.◯
3.×
ヒストグラムは、ばらつきをもつデータの範囲をいくつかの区間に分け、各区間を底辺とし、その区間で出現度数を高さとした長方形(柱状)を並べた図で、柱状図とも呼ばれる。データの分布の形を見たり、規格値との関係(目標値からのばらつき状態)をみることができる。計量特性の度数分布のグラフ表示で、製品の品質の状態が規格値に対して満足のいくものか等を判断するために用いられる。
観測値若しくは統計量を時間順またはサンプル番号順に表し、工程が管理状態にあるかどうかを評価するために用いられる図は、管理図である。
対応する2つの特性を横軸と縦軸にとり、観測値を打点して作るグラフ表示で、主に2つの変数間の相関関係を調べるために用いられるのは、散布図
である。
4.◯
[ No.46 ]
仕上工事における試験及び検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1. アルミニウム製外壁パネルに施された陽極酸化皮膜の厚さは、渦電流式測定法により測定した。
2. 現場搬入時の造作材の含水率は、高周波水分計を用いて15%以下であることを確認した。
3. 防水形仕上塗材仕上げの塗厚の確認は、単位面積当たりの使用量を基に行った。
4. 塗装素地となるモルタル面のアルカリ度は、pHコンパレーターを用いて塗装直前にpH12以下であることを確認した。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
2.◯
3.◯
4.×
塗装下地のコンクリート、モルタル面のアルカリ度はpH9以下とする。
pH(ペーハー):
酸性、アルカリ性の程度を表す単位す。
pHは0から14までの数値で表され、pH7が中性、7より小さいと酸性、大きいとアルカリ性となる。
[ No.47 ]
市街地の建築工事における公衆災害防止対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1. 防護棚は、水平面に対して角度を20°とし、外部足場の外側から水平距離で1.8mはね出しとした。
2. 鉄骨躯体の外側に設置する垂直ネットは、日本産業規格(JIS)に適合した網目寸法15mmのものを使用した。
3. 建築工事を行う部分の高さが地盤面から20mのため、防護棚を2段設置した。
4. 防音パネルを取り付けた枠組足場の壁つなぎの取付け間隔は、垂直方向3.6m以下、水平方向3.7m以下とした。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
防護柵は、骨組の外側から水平距離で 2m以上突き出させ、水平面とのなす角度を 20° 以上とし、風圧、振動、衝撃、雪荷重等で脱落しないように骨組に堅固に取り付ける。(建設工事公衆災害防止対策要綱建築工事編第4章第28四)
2.◯
3.◯
4.◯
[ No.48 ]
事業者の講ずべき措置に関する記述として、「労働安全衛生規則」上、誤っているものはどれか。
1. 3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
2. 高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。
3. つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、脚部の沈下及び滑動の状態について点検を行わなければならない。
4. 高さ又は深さが1. 5mをこえる箇所で作業を行うときは、原則として、安全に昇降できる設備を設けなければならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
2.◯
3.×
事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、同規則第567条第2項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないと規定されている。(労働安全衛生規則第568条)
しかし、同規則第567条第2項で脚部の沈下及び滑動の状態は第六号に、建地、布及び腕木の損傷の有無は第八号に規定されているため、つり足場における作業開始前の点検項目から除外されている。
☆令和5年10月1日施行の同規則第567条・第568条の改正により、事業者が自ら点検する義務が、点検者を指名して、点検者に点検させる義務に変更された。したがって、現在では、この部分が誤りとなる。
4.◯
[ No.49 ]
クレーンを用いて作業を行う場合に事業者の講ずべき措置として、「クレーン等安全規則」上、誤っているものはどれか。
1. つり上げ荷重が0.5tのクレーンの玉掛用具として使用するワイヤロープは、安全係数が6のものを使用した。
2. つり上げ荷重が0.5t以上5t未満のクレーンの運転の業務に労働者を就かせるため、当該業務に関する安全のための特別の教育を行った。
3. 強風により移動式クレーンが転倒するおそれがあったため、作業を中止してジブの位置を固定させる措置を講じた。
4. 移動式クレーンの運転についての合図の方法は、事業者が指名した合図を行う者に定めさせた。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
2.◯
3.◯
4.×
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、原則として、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならない。ただし、運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りでない。(クレーン等安全規則第71条第1項)
指名されたものが合図を定めるのではなく、定めるのは事業者である。
[ No.50 ]
有機溶剤等の使用及び貯蔵に関する記述として、「有機溶剤中毒予防規則」上、誤っているものはどれか。
1. 有機溶剤濃度の測定を必要とする業務を行う屋内作業場については、6月以内ごとに1回、定期に、濃度の測定を行わなければならない。
2. 有機溶剤業務に係る局所排気装置は、3月を超えない期間ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
3. 有機溶剤等を屋内に貯蔵するとき、有機溶剤等が発散するおそれのない蓋又は栓をした堅固な容器を用いるとともに、有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備を設けなければならない。
4. 使い終わった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、当該容器を密閉するか、又は当該容器を屋外の一定の場所に集積しておかなければならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
2.×
屋内作業場等で有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、作業場所に、有機溶剤の蒸発の発生源を密閉する設備、局所排気装置を設けなけらばならない。有機溶剤作業主任者の職務として、局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検しなければならない。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2第二号)
3.◯
4.◯