問題6の攻略 法規 択一問題 3問
法規は、建設業法、建築基準法施行令、労働安全衛生法からそれぞれ1問ずつ出題されて、それぞれ2箇所の選択部分があります。
押さえておくべき内容(過去問題より)
1) 建設業法
(1) 用語の定義(2条)
【1】建設工事
【2】建設業・建設業者
【3】下請契約
【4】発注者
(2) 建設業の許可(3条)
附帯工事 (4条)
(3) 請負契約の原則
・現場代理人の選任等に関する通知(第19条の2)
・建設工事の見積り等(第20条)
・下請負人の変更請求(第23条)
・請負契約とみなす場合(第24条)
(4) 下請代金の支払〜検査・引渡し・監督
・下請代金の支払(24条の3)
・検査及び引渡し(24条の4)
・特定建設業者の下請代金の支払期日等(24条の6)
・下請負人に対する特定建設業者の指導等(24条の7)
(5) 施工体制台帳と技術者の配置
・施工体制台帳及び施工体系図の作成等(第24条の8)
・主任技術者及び監理技術者の設置等(第26条)
・主任技術者及び監理技術者の職務等(第26条の4)
2) 建築基準法施行令
(1) 仮囲い(第136条の2の20 )
(2) 根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止(第136条の3 )
(3) 基礎工事用機械等の転倒による危害の防止(第136条の4)
(4) 落下物に対する防護(第136条の5 )
(5) 建て方(第136条の6 )
(6) 工事用材料の集積・火災の防止(第136条の7・第136条の8)
3) 労働安全衛生法
(1) 事業者等の責務 (第3条)
(2) 総括安全衛生管理者 (第10条)
(3) 元方事業者の講ずべき措置等(第29条)
(4) 特定元方事業者等の講ずべき措置(第30条)
(5) 安全衛生教育 (60条)
(6) 健康診断 (66条)
(7) 快適な職場環境の形成(71条の2)
建設業法
建設業法からは、請負契約に関する20条から技術者の設置に係る26条の4までが出題の中心となり、出題実績がある条文の数は12条程度ですので、比較的、的がしぼりやすいといえます。
(1) 用語の定義(2条)
【1】建設工事
建設工事とは、土木建築に関する工事で別表で定める下表の29業種のいずれかとなる。建設業の許可は、この29業種ごとに必要となる(3条2項)。
【2】建設業・建設業者
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいい、建設業者とは、許可を受けて建設業を営む者をいう。
【3】下請契約
下請契約とは、建設工事を他の者(発注者)から請け負った建設業を営む者(元請業者)と他の建設業を営む者(下請業者)との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
【4】発注者
発注者とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
(2) 建設業の許可
【建設業の許可】
第3条
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府喋の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
ー 建設業を営もうとする者であって、次号に褐げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。z
【附帯工事】
第4条
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
(解 説)
【1】3条1項本文
本条は、営業所の設置場所による許可の区分と、許可不要となる軽微な建設工事を示している。
● 複数の都道府県に営業所を設置・・・国土交通大臣の許可
● 1つの都道府県に営業所を設置・・・当該都道府県知事の許可
許可を要しない軽微な建設工事は、請負代金が500万円以下(建築ー式工事の場合は1,500万円以下)又は延べ面積150m2未満の木造住宅の建築工事と、施行令1条の2で定められています。
【2】3条1項一号 ニ号
建設業の許可は、下請金額により、一般建設業(一号)と特定建設業(二号)に区分されることを示している。
● 特定建設業の許可・・・下請金額が4,500万円以上(建築ー式工事の場合7,000万円以上)
● 一般建設業の許可・・・上記以外
【3】3条2項、4条
建設業の許可は、前掲の29業種ごとに必要と定めている。その上で、4条は附帯工事である場合(屋根工事の附帯としての板金工事等)は許可外の工事も請け負える旨を示している。
(3) 請負契約の原則
【現場代理人の選任等に関する通知】
第19条の2
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。
2 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第4項において「監督員に関する事項」という。)を、書面により請負人に通知しなければならない。
【建設工事の見積り等】 (H27・30)
第20条
建設業者は、建設工事の諾負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
【下請負人の変更請求】
第23条
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
【請負契約とみなす場合】 (R3)
第24条
委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
( 解 説 )
【1】現場代理人の選任等に関する通知(19条の2)
工事現場に請負人が現場代理人を置き(1項)、又は注文者が監督員を置く場合(2項)、その権限及び行為に関する意見の申出の方法について、それぞれ相手方に通知すべきと定めている。
【2】建設工事の見積り等(20条)
請負契約に際して、工事の種別ごとの材料費、労務費等の経費の内訳、工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行う努力義務を定めている。
また、2項では、注文者から請求があった場合、請負契約が成立するまでに見積書を交付しなければならない旨を定めている。
【3】下請負人の変更請求(23条)
あらかじめ書面で承諾した下請負人を除き、注文者は、著しく不適当な下請負人の変更請求ができる旨を示している。
(4) 下請代金の支払〜検査・引渡し・監督
【下請代金の支払】 (R5)
第24条の3
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
2 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
3 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう 適切な配慮をしなければならない。
【検査及び引渡し】 (H26・R2)
第24条の4
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
2 元請負人は、前項の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
[特定建設業者の下請代金の支払期日等】 (H25・R4)
第24条の6
特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第24条の 4第2項の申出の日(同項ただし書の場合にあっては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
2 特定建設業者が注文者となった下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかったときは第24条の4第2項の申出の日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは同条第2項の甲出の日から起算して50日を経過する日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
[下請負人に対する特定建設業者の指導等】
第24条の7
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
2 前項の特定建設業者は、その請け負った建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。
3 第1項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該 建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を菅轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。
( 解 説 )
【1】下請代金の支払(24条の3)
元請負人が出来形部分又は全部の報酬の支払いを注文者から受けている場合を前提に、その受領の日から1カ月以内でできる限り短い期間に下請負人に支払いをすべきと定めている。その場合、労務費(労働人件役)は現金での支払いを求めています(2項)。
3項は、元請負人が注文者から前払金を受けている場合の規定です。
【2】検査及び引渡し(24条の4)
下請負人から完成通知があった場合、元請負人は、通知から20日以内でできる限り早く完成確認の検査を完了すべきと定めている(この検査は、建築基準法の完了検査等ではなく、請負契約上の行為です)。
2項では、検査確認後に下請負人から引き渡す旨の申出があれば、直ちに引渡しを受けなければならない旨が示されているが、引渡し時期の特約があれば、その特約に従うことになる。ただしその特約は、契約で定めた完成時期から20日以内のものに限るとされています。
【3】特定建設業者の下請代金の支払期日等(24条の6)
特定建設業者が注文者となる下請契約(下請負人も特定建設業者等の場合を除く)の下請代金の支払期日を定める場合、下請負人からの引渡しの申出の日から起算して50日以内で、かつ、できる限り短い期間内で定めるよう示している。
2項では、下請代金の支払期日の定めがない場合、下請負人からの引渡しの申出の日が支払期日とみなされると定めている。また、上記の支払期日の定めに違反した支払期日が定められたときは、引渡しの申出の日から50日を経過する日が支払期日と定められたものとみなすとして、下請負人を保護している。
なお、本規定は「特定建設業 → 一般建設業」の場合のみ適用され、
「特定 → 特定」や「一般 → 一般」の場合には適用されない。
「特定 → 特定」や「一般 → 一般」の場合には適用されない。
【4】下請負人に対する特定建設業者の指導等(24条の7)
特定建設業者の下請負人の監督方法として、指導義務、是正要求及び許可権者に対する通報が定められている。
(5) 施工体制台帳と技術者の配置
[施工体制台帳及び施工体系図の作成等] (H29・R6)
第24条の8
特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交適省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負った建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
3 第1項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があったときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
4 第1項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
【主任技術者及び監理技術者の設置等】
第26条
建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第3条第1項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第 15条第二号イ、口又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあっては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前2項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあっては、発注者から直接当該建設工事を請け負った特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第26条の4第1項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第15条第二号イ、口又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該エ事現場に専任で置くときは、この限りでない。
4 前項ただし書の規定は、同項ただし書の工事現場の数が、同一の特例監理技術者(同項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。次項において同じ。)がその行うべき各工事現場に係る第26条の4第1項に規定する職務を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。
5 第3項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(特例監理技術者を含む。)は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、第26条の5から第26条の7までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
6 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
【主任技術者及び監理技術者の職務等】 (H28・R1)
第26条の4
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
( 解 説 )
【1】施工体制台帳及び施工体系図の作成等(24条の8第1項・3項・4項)
特定建設業者は、下請金額が4,500万円(建築ー式工事の場合は7,000万円)以上の場合、所定の施工体制台帳と施工体系図を作成し、公開する必要があります。
【2】主任技術者の設置(26条1項)
建設工事の施工現場には、建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者の配置義務があることを定められています。なお、建設業社でない場合には、この義務はありません。
【3】監理技術者の設置(26条2項)
特定建設業者は、施工体制台帳の場合と同様に下請金額が4,500万円(建築ー式工事の場合は7,000万円)以上の場合、その現場に監理技術者の配置義務を負う旨を定めている。
【4】専任の技術者の設置(26条3項・4項)
公共施設又は多数の者が利用する施設等の所定の重要な建設工事については、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任と定め、兼任を禁止して います。ただし、特定建設業者が施工管理技士補を工事現場に専任で置くときは、監理技術者は2つの現場まで兼任することが容認されています。
4項と5項は、専任の監理技術者の要件と監理技術者証に関する規定です。
【5】主任技術者及び監理技術者の職務等(26条の4)
主任技術者及び監理技術者の職務について規定しています。
建築基準法施行令
建築基準法施行令は、第7章の8「工事現場の危害の防止」から出題されています。この章は7つの条文によって成り立っていますので、建設業法よりもさらにしぼりやすいといえます。
(1) 仮囲い (H27・30)
(2) 根切り工事・山留め(H29・R2・5)
(3) 基礎工事用機械等の転倒による危害の防止
(4) 落下物に対する防護(H25・26・R1・4)
(5) 建て方 (H28・R3・6)
(6) 工事用材料の集積・火災の防止
(1) 仮囲い
【仮囲い] (H27・30)
第136条の2の20
木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
( 解 説 )
木造建築物は高さ13m又は軒高9m超、非木造は2階以上の建築物の工事に際して、高さ1.8m以上の仮囲いが原則として必要と規定されています。なお、現場地盤面が周辺より低い場合は、高い工事現場の周辺から1.8mを符定します。
(2) 根切り工事・山留め
【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】 (H29・R2・5)
第136条の3
建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
4 建築工事等において深さ1.5m以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならなしい。
6 建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、排水を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。
( 解 説 )
1項、4項、6項ともに、根切り、山留め工事の場合の注意事項を規定しています。なお、未出題ですが、その他の項も詳細な注意事項を規定しています。
(3)基礎工事用機械等の転倒による危害の防止
【基礎工事用機械等の転倒による危害の防止】
第136条の4
建築工事等において次に掲げる基礎工事用機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものに限る。)又は移動式クレーン(吊り上げ荷重が0.5t以上のものに限る。)を使用する場合においては、敷板、敷角等の使用等によりその転倒による工事現場の周辺への危害を防止するための措置を講じなければならない。ただし、地盤の状況等により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
一 くい打機
二 くい抜機
三 アース・ドリル
四 リバース・サーキュレーション・ドリル
五 せん孔機(チュ_ビングマシンを有するものに限る。)
六 アース・オーガー
七 ペーパー・ドレーン・マシン
八 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通大臣が定める基礎工事用機械
( 解 説 )
現時点では未出題ですが、敷板、敷角等の使用等で転倒防止を図る旨が規定されている点に注意しておきましょう。
(4) 落下物に対する防護
【 落下物に対する防護 】 (H25・26・R1・4)
第136条の5
建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが3m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシュートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。
2 建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面から高さが7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
( 解 説 )
1項はダストシュートの設置要件、2項はいわゆる足場シート等の設置要件等が規定されています。
(5) 建て方
【建て方】 (H28・R3・6)
第136条の6
建築物の建て方を行なうに当たっては、仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
2 鉄骨造の建築物の建て方の仮締は、荷重及び外力に対して安全なものとしなければならない。
( 解 説 )
建築物の建方の際の事故防止のため、仮筋かいや仮締等を規定しています。
(6) 工事用材料の集積・火災の防止
【工事用材料の集積】
第136条の7
建築工事等における工事用材料の集積は、その倒壊、崩落等による危害の少ない場所に安全にしなければならない。
2 建築工事等において山留めの周辺又は架構の上に工事用材料を集積する場合においては、当該山留め又は架構に予定した荷重以上の荷重を与えないようにしなければならない。
【火災の防止】
第136条の8
建築工事等において火気を使用する場合においては、その場所に不燃材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。
( 解 説 )
いすれも未出題ですが、条文は一読しておきましょう。
労働安全衛生法(安衛法)
安衛法は、事業者の責務といった視点からの条文が出題の中心となっており、出題実績がある条文は7つほどしかありません。ただ、比較的なじみの薄い法律であり、出題にクセがあるため、法規の中では最も難度が高いといえます。
(1) 事業者等の責務(H30)
(2) 総括安全衛生管理者 (R2・5)
(3) 元方事業者の講ずべき措置等(H27・R3・4)
(4) 特定元方事業者等の講ずべき措置(H26・R1)
(5) 安全衛生教育(H25・29)
(6) 健康診断(H28)
(7) 快適な職場環境の形成(R6)
(1) 事業者等の責務
【事業者等の責務】 (H30)
第3条
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国 が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
2 機械、器貝その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
( 解 説 )
労働現場を管理する事業者に対する包括的な規定であるとともに、3項は注文者に対しても不適切な発注をしない責務を規定しています。
(2) 総括安全衛生管理者
【総括安全衛生管理者】 (R2・5)
第10条
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
( 解 説 )
総括安全衛生管理者は、常時100人以上の労働者を使用する事業場に選任すべき者で、安全管理者や衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険又は健康障害を防止するための一号から五号の業務を統括管理します。
(3) 元方事業者の講ずべき措置等
【元方事業者の講ずべき措置等】 (H27・R3・4)
第29条
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。
3 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。
第29条の2
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
( 解 説 )
元方事業者とは、いわゆる元請負人であり、関係請負人の労働者とは、下請の労働者のことです。本来の雇用関係にはない下請の労働者についても、元方事業者は、安全・衛生を維持・確保するため指導をし、是正を指示しなければならず、当該労働者もこれに従わなければなりません。さらに、元方事業者は下請会社の労働者が危険な場所で作業を行う場合は、下請会社が講ずべき危険防止措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他必要な措置をしなければならないとする規定です。
(4) 特定元方事業者等の講ずべき措置
【特定元方事業者等の講ずべき措置】 (H26・R1)
第30条
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
( 解 説 )
特定元方事業者とは、いわゆる建設業などの特定業種の元請負人のことです。通常、下請が介在することが想定される業種であるため、労働災害の防止のために、29条、29条の2と同趣旨でさらに詳細に関係請負人との関係を規定しています。
(5) 安全衛生教育
【安全衛生教育】(H25・29)
第60条
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
( 解 説 )
一定の危険性がある職務に新たに就くこととなる職長等に対し、事業者は、安全・衛生に関する一号から三号の教育を実施しなければならないとする、いわゆる職長教育の規定です。なお、作業主任者はその職務について別途教育を受けているため、除外されています。
(6) 健康診断
【健康診断】(H28)
第66条
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
( 解 説 )
労働者に対して健康診断を実施しなければならない事業者の義務が規定されています。2項は特に有害な業務について、医師による特別な項目についての健康診断が規定されています。
(7) 快適な職場環境の形成
【事業者の講ずる措置】(R6)
第71条の2
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
一 作業環境を決適な状態に維持管理するための措置
二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
( 解 説 )
事業者は、快適な職場環境を形成するため、作業環境を快適な状態に維持管理する措置、作業方法を改善する措置、疲労を回復するための施設又は設備の設置又は盤備、その他快適な職場環境を形成するため必要な措置を講じなければいけません。

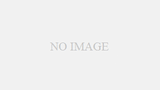
コメント