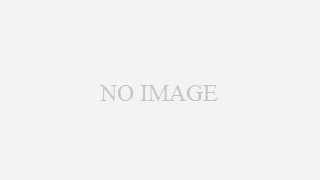 04章 地業工事
04章 地業工事 4章 地業工事 1節 一般事項
1節一般事項4.1.1 適用範囲地業工事では、基礎や基礎スラブを支えるために、それより下の地盤に設けた各種の杭、砂利、砂及び捨コンクリート地業、並びにこれらに関する試験を対象としている。4.1.2 基本要求品質(a) 杭地業工事で使用する材...
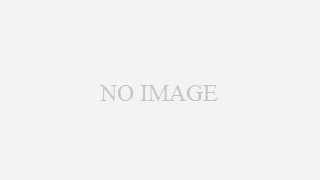 04章 地業工事
04章 地業工事 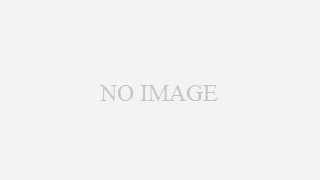 04章 地業工事
04章 地業工事 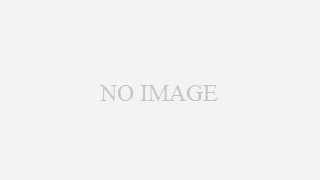 04章 地業工事
04章 地業工事 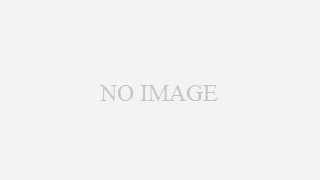 04章 地業工事
04章 地業工事 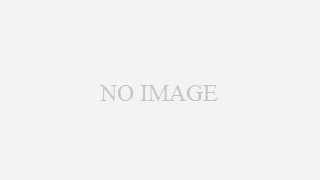 04章 地業工事
04章 地業工事 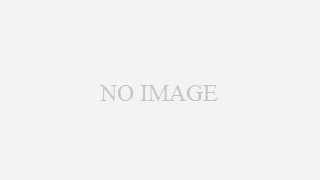 04章 地業工事
04章 地業工事 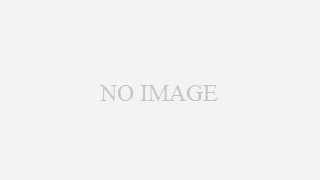 04章 地業工事
04章 地業工事 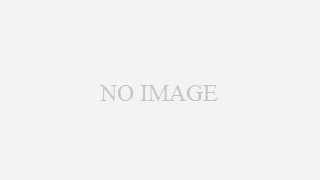 概 要
概 要 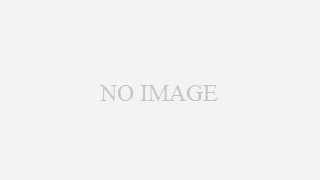 05章 鉄筋工事
05章 鉄筋工事 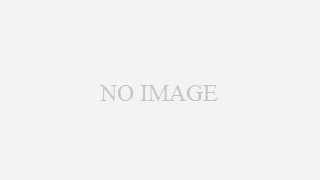 05章 鉄筋工事
05章 鉄筋工事