問題4の攻略 躯体施工 記述問題
1年おきに「躯体施工」と「仕上施工」の出題形式が 入れ替わりながら出題されており、問題4は留意事項の記述、問題5は択ー形式というかたちになっております。
昨年(令和6年)は、「仕上施工」が問題4で留意事項の記述、「躯体施工」は問題5が択ー形式でしたので、今年(令和7年)は、
問題4 躯体施工 留意事項の記述形式
問題5 仕上施工 択ー形式
になるものと考えられます。
過去の出題例より
地業工事
【 地盤アンカーを用いる場合の施工上の留意事項 】
①敷地境界からアンカー部分が出る場合、事前に隣地管理者等関係者の了解を得て施工する。
② 地盤アンカーの引抜き耐力は、全数について設計アンカー力の1.1倍以上であることを確認する。
③ 山留め壁には鉛直力が作用することから、山留め壁は十分な鉛直支持性能を有する地盤に支持させる。
【 山留め壁に鋼製切梁工法の支保工を設置する際の留意事項 】
① 腹起しは連続して設置することとし、継手の設置位置は曲げ応力の小さい箇所となるようにする。
② 切りばりの継手は切りばり支柱間に2ヵ所以上設けないようにし、同一方向の継手は同じ位置に並ばないようにする。
③ 接合部が変形している場合は、端部の隙間にライナーなどを挿入し、切りばりの軸線が直線になるようにする。
鉄筋工事
【 バーサポート又はスペーサーを設置する際の施工上の留意事項 】
①使用部位や所要かぶり厚さに応じて、スペーサーの材種や形状・サイズを使い分ける。
②スラブに用いるバーサポート及びスペーサーの材種は、原則として、コンクリート製か鋼製とする。
③ 下端が打放し仕上げとなる場合のスラブ用スペーサーは、露出面が大きくならないようなものを使用する。
コンクリート工事
【 支保工にパイプサポートを使用する場合の施工上の留意事項 】
① 支柱は垂直に立て、上下階の支柱は平面上の同一の位置とする。
② パイプサポートは3本以上継いではならない。
③ 高さが 3.5mを超えるパイプサポートには、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ、つなぎの変位を防止する。
【 コンクリートを密実に打ち込むための施工上の留意事項 】
① 1層の打込み厚さは、公称棒径 45mmの棒型振動機の長さ( 60~80mm)以下とし、打ち込んだコンクリートの下層まで振動機の先端が入るようにする。
② コンクリートは打込む位置の近くに落とし込むようにし、1箇所に多量に打ち込み、横流ししないようにする。
③ コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は、外気温が 25°C以下の場合 120分以内、25°C を超える場合は 90分以内とする。
【 コールドジョイントの発生を防止するための施工上の留意事項 】
① 練混ぜから打込み終了までの時間の限度(外気温 25℃以下の場合 120分、外気温 25℃超える場合 90分)を厳守する。
② 打重ねの時間間隔の限度(外気温 25℃未満の場合150分、外気温 25℃以上の場合120分)を厳守する。
③ 打重ね時は、棒形振動器の先端を先に打ち込んだ層まで挿入する。
鉄骨工事
【 仮ボルトの施工上の留意事項 】
① 本締め用の高力ボルトを仮ボルトに兼用してはならない。
② 高力ボルト継手(高力ボルト接合)では、中ボルト等を使用してボルト1群に対して 1/3程度かつ2本以上をバランスよく配置して、締め付ける。
③ 溶接継手におけるエレクションピース等に使用する仮ボルトは、高力ボルトを使用して全数締め付ける。
【 頭付きスタッドをアークスタッド溶接する場合の施工上の留意事項 】
① スタッド溶接は、アークスタッド溶接の直接溶接とし、原則として、下向き姿勢とする。
② 溶接面に、著しい錆・塗料・亜鉛めっき等がある場合は、グラインダー等により除去する。
③ 午前と午後の作業開始前に、適切な溶接条件を確認するために試験溶接を行う。
【 建入れ直しを行う場合の施工上の留意事項 】
① 建入れ直しのために加力するときは、加力部分を養生し、部材の損傷を防止する。
② ターンバックル付き筋かいを有する場合は、その筋かいを用いて建入れ直しを行わない。
③ 建入れ直しは、溶接歪みなどを考慮した本接合終了後の精度を満足できるように行う。

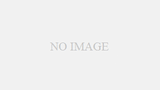
コメント